この作品は拙作[平蔵・月の都に住む人は]を踏まえています
 |
「ミス・ダウト」 |
 |
光彦は廊下を小走りに過ぎ去る人影を複雑な思いで見送った。
1年生の、可愛いと評判だった少女だ。うつむいて…泣いていたのだろうか。耳が真っ赤だった。
化学準備室で何があったのかは容易に想像がつく。ほっと溜め息をついた。
「主席卒業おめでとう。密かに鼻が高いわ」
振り返った少女は眩しそうに目を細めた。陶器のように白い肌の中で、猫科の生き物のようなまっすぐでいて不思議な彩光を放つ瞳がその影をひそめる。
見慣れたものなのに、途端に心臓がどくんと強く打つ。それを悟られたくなくて、少女の背を通りすぎ、窓辺のシンクに半分腰をかける形で寄りかかった。
「灰原さんが手を抜いてくれたからの主席じゃないですか」
少し嫌味に言ってやると、かすかに笑みと呼べそうなものが唇の端に浮かんだ。大人びている、と密かに慕う者の多い感情の示し方。男子校でもないのに少女は年下の娘達の憧れのまとで、毎年バレンタインにはハンパで無い数のチョコレートが贈られるのを知っていた。整った容姿と、年にふさわしからぬ鋭利な思考、そして、さらにそれらに不似合いに見える奇妙なまでのこまやかな気遣い。12年間、傍で見詰めてきたから誰よりも知っている。
「現国やグラマーが苦手なのはわかってるでしょ。真面目に勉強してきたつもりよ?それでも貴方には敵わなかったわね」確かに、今だって手の中には直前対策の参考書がある。まぁあまり熱心にその活字を拾っていたとも言いがたいが。「博士には"やっぱり円谷君だった"って報告しておくわね。きっと二次が終わったらお祝いをしようって言い出すわよ」
「せっかちですね。普通、発表が終わってからじゃないんですか」
苦笑して少女の保護者を評すると、少女は肩をすくめた。
「発表の後には改めて合格祝いをするの。皆大人になってあまり訪ねて来てくれなくなったから淋しいのよ、集まる口実は逃さないわ」
「…博士だって忙しいでしょう、」光彦は少し後ろめたい思いで言い訳を探した。少年達の好奇心を誰よりもわかってくれ、何より自らが幼い日の“無意味なもの”に対する情熱を忘れていなかった人。少女の保護者というだけではなく、確かに彼は自分達の遊び友達だったはず。つい新しい生活環境の中で後回しになっていってしまったけれど。「確か、去年のクリスマスでヒットしたおもちゃ、博士の特許の商品化だったんですよね?」
「そうよ、メーカーの売上を考えると微々たる報酬だと思うけど。いずれにしても、博士には納品してしまえばもう過去のものだから。そのころからずっと、少年探偵団のメンバーも高校卒業だなぁ、って何か皆に贈るものを考えてたみたい」
「申し訳ないなぁ…」
「適当に連絡するから、時間、出来ればつくって?」
「ええ、もちろんです」
光彦は勢い込んで答えた。
少女は微笑んで、資源ゴミになるまであと数日の命の冊子を早くも投げ出し、天頂に上り詰めようという光の中で伸びをした。制服のネクタイを少し緩めているので、白い喉が気持ちよさげに晒される。光彦は慌てて目をそらせた。
「…灰原さんからは、」
「え?」
「灰原さんからは貰えませんか」
視界に彼女がいないことに助けられて、思わず飛び出した請願。
「もちろんあげるけど…なぁに、リクエストがあるの?」
「…言葉を」
「…え?」
組んだ手をそのままに、少女は怪訝そうに身体を起した。
「…教えて欲しいんです。いや、嘘をつかないでいてくれればいい」
「…」
「灰原さんは、コナン君と…行くのかと思っていました」
光彦の口から出たあまりにも遠い名前は少女に一瞬言葉を忘れさせた。それは12年前の学友。罪と希望との二つがマーブリングのように分かちがたく彩った季節にいた幻の少年の名。
「…行く?」
「コナン君がブラジルの御両親のところに行ってしまった後、灰原さんも学校を長期間休みましたよね。あの時、僕は"ああ、やっぱり"って思ったんです」
「だから、あれは…私もうちのことでごたごたしてて…」
「灰原さん」
光彦は静かに言葉を遮った。
「…そうか、そうね。お祝い、だったわね」
少女は唇を噛んだ。そのまま目を薬品棚に投げる。辛抱強く答えを待つ光彦の視線を頬に感じながら。
いつか告げなければならないだろうと覚悟してきたつもりだった。そして、その日が近いことも知っていて…逃れられるものなら、そ知らぬ振りをしてしまえるのではないかと自分を騙してきた。少年と自分を同じ制服に包んでいたあたりまえの“日常”。
「…ついさっきだって…自分から…はみ出す事をしていて、ずるいわね」
自嘲的に呟く。知っていたのだ、そこまで欺き切れない自分自身を。
少年に向って真正面に座り直す。
今…ここで糸が切れてしまったら、もう少年との接点は得られまい。制服の時間はもう終わった。誰も二人を同じ門の中に追いやる事は出来ない。
同じ大学を受験するはずだったけれど、彼が望まないとき、自分は彼と同じ道を選ぶわけにはいかない。
瞼の裏に12年分の感謝を刻む。
そして、少女は感情の起伏の淡い、長い物語をはじめた。
家族のこと。
白衣が身体に馴染むほどに打ちこんだ研究のこと。
その顛末と、少年達との出会い。
小説より「奇」な一人の名探偵の運命のこと。
そして、自分が捨てた12年の時間のこと。
もう一度APTX4869を飲むこと、それは人が聞いたら馬鹿げていると思ったかもしれない。けれど、本当は…刑の執行であり、賭けだったのだ。
あの日、“志保”の身体で受け取った“あの人”の言葉。 罪に対する死刑の宣告。
…その後に恩赦がある確率は1パーセントにも満たなかった。
7歳の少女として裸足で帰った朝、ずっと保護者をかって出てくれていた人は涙腺が壊れたかと思えるほど泣いて抱きしめてくれた。そして涙が枯れると同時に、養女とする手続きのため東奔西走してくれた。
だから。
実験机の日溜りの中に転がしてある卒業証書の名前は“阿笠
愛”。
光彦はつくづくと愛を眺めた。18歳の時、と言われて思い浮かぶのは今眼前にいる女性の姿だけだった。無理にでもあの日から逆に時計を回せと言われても、そこで像を結ぶのは同じ姿だった。絹のような赤みがかった髪をまっすぐに鎖骨のあたりでゆらす少女。それ以外の愛がいるはずがなかった。
「それが…“アダルトな会話”の真相だったわけですね」
光彦は変わらずに静かに言う。
「歩美にも…話したほうがいいのかしら」
高校進学で進路が分かれてしまったけれど、吉田歩美との交友は続いている。何度か街で行き会った歩美の友人達が二人の繋がりがわからないと首をかしげていることは知っていたが。
「歩美ちゃんには…言わなくてもいいと思います」
光彦はそっと囁いた。
高校で、愛は弓道部に入った(化学準備室に出入りしているのは単なる趣味である)。歩美に誘われたから、だ。なかなか友人らしいものが出来なかったのに、急に同級生に馴染めるようになったのは梅雨のあとさきに歩美の高校と練習試合があってから。二人の応援と称して覗きに行った光彦は知っている。歩美と素直に語り合う彼女を見てようやく周囲が安心したのだと。
「コナン君がいるんなら歩美ちゃんにも必要な真実だと思いますけど…」
初恋の匂いがする名前のとり合わせ。誰もが幼い思慕の受け取り手を得られずに、世界で自分が一番辛い恋をしていると信じていていた季節。そんなサークルゲームの中心にいた少年はフライングして去り、光彦の前には次第に存在を大きくしていく女性が残った。
「…なんで?」
「え?」
「なんで笑うの?犯罪者だったと…そう私は言ったのよ?貴方達を騙していたの。そんな風に…“ちょっとした秘密”じゃないわ!?」
「…罵って欲しいんですか?」
愛は叱られた小動物のように小さく首をすくめた。
「僕は自分を信じています。たぶん歩美ちゃんも、ね。
つい一時間前まで慕っていた人の、過去を聞かされたからといって手のひらを返したような接し方をするようなそんな浅はかな人間じゃないつもりですよ。
第一…自分で言ったんですよ、刑は執行された、と。その結果として、今の灰原さんには“この場所”がある。なのに過去にこだわるなんて…そんなに僕等を低俗な人間にしたいですか」
「円谷君…」
光彦は、日陰に置いておいた花束からわずかに綻んだサーモン・ピンクの薔薇を一本抜き取る。
「…この花がどんな場所でどんな風に育てられたか、なんて、僕達は知らない。
でも、綺麗だということはわかる。そして、その美しさに想いを託すことも」
差し出されたそれを反射的に受けとってしまい、慌てて顔を上げた愛は、そこに見出した照れたような笑顔に、はっとしてあえいだ。
今、見つけた暖かいものを愛惜しむ自分の感情の強さに息が止まる思いだった。
大人びた言葉。それは偽りの日々の自分たちのような乾いたものではなくて、初めて出会ったときから背伸びをしていても少年自身の言葉だった。今、少年らしい熱さを垣間見せつつ、制服にそぐわないすがしい強さを見せるのは…離れた方がいいのかもしれないと思いつつも、共にあることをやめられなかった自分の所為だと微かな痛みに思う。
失いたくなくて、言えないことがある。
だが、言わない限り、自分が"それ"と向き合えないことも悲しく悟る。
「…工藤君に惹かれていたわ。
組織では思考であたしに敵う人間はほとんどいなかったから…探偵としての冴えと、その真実を追う姿勢の強靭さに。科学者に少し似ているでしょ、そういうところって。
でも…いつの間にか、6歳児という押しつけられた役柄にも、さらにはすべての根源である女と小学校の教室で同級生を演じる事を押し付けられても…飄々と生きていかれる勁さや、そこに同居している優しさに」
「ええ…言葉は乱暴だったけれど」
光彦は困ったように微笑んだ。憎らしかったライバルが実は今を時めく人物だったと聞かされては、ぼやきの言葉も向うところを見失ってしまう。
「…いつか追いつこう、そうしたら…と思っていたけれど、絶対に追いつけない距離だったなんて…かなり悔しいかな。でも…ま、いいです。僕は僕なりに努力し続けるだけです」
追いつきたかったのは愛。
追い越したかったのはコナン。
「もっと早くに言うべきだった…わね」
肩の荷を下ろしたように愛が囁く。
「えっ…それならば、祝いに別のものをねだるんだったな…失敗しました」
「あら、いいわよ?」
「…」
光彦はあらぬ方をみやった。本当は言いたい事がある。ずっとずっと…願ってきた。
話して欲しかった“もうひとつのこと”を愛が自分から言ってくれた今、形にすることを許されたのだと思いたいのだけれど。
「ええと…さっき、こちらへ来る前に下級生とすれ違ったんですけど」
「…」
愛は目を細めた。
察しの良いことは時々困ったけれど、こんな時だけは感謝したい。
直接的な言葉は、どうやっても己の口から出す事ができない。
「…それはダメ」
「そ、そうですかっ、そうですよねぇ…は、は…」
もはや何に笑っているのかよくわからなくなった光彦だったけれど、顔をそむけた愛が、小さく続けた言った言葉はちゃんとキャッチできた。
「だって男の子から…するものでしょ」
耳を疑うけれど、白い頬に微かに差した赤みと、無言の光彦の方をがんとして見ないことが何より雄弁に意図したものを示している。
「…」
光彦はそっと壊れ物を手に取るように腕を伸ばした。
ふれた頬のすべらかさ。自分の方へ向けさせるのも惜しくて、身体を乗り出した。
机の上に片腕をついて、ぎこちなく口吻ける。
睫毛が微かに震えるのが愛惜しかった。
舌が優しく唇をつついた時、光彦の背に回された腕から慌てたように力が抜けたのがわかる。
名残惜しさが身体の中心を渦巻いたけれど、光彦はそっと淡い肩を押した。
「…阿笠愛が男の人としたファースト・キスよ?」
と少し怒ったような愛。
「次も…予約して良いですか?」
「馬鹿ね…」
「ああ、失礼。一生分予約しますから」
しれっと言って見せると、愛は…わずかに眉をひそめた。
呆れ顔と、嬉しい顔と、どっちも一度にしようとして失敗したのがわかる。
「さぁ、帰りましょうか」
光彦はくすっと笑って、愛の卒業証書を引き寄せた。
通いなれた道を制服で歩くのも最後だ。
部活の追い出し会で遅くなった生徒がちらほらいるだけの道。本当は手を繋いでみたかったけれどそれは早々に諦めた。光彦は生徒会の後輩や顔もろくに覚えていないような女生徒から、愛は弓道部の後輩とやはり顔も覚えていない女生徒(!)から貰った花束やらプレゼントやらで両手がふさがっていたのだから。
銀杏と染井吉野が交互に植えられた道。枝の先はまだ紅を差してもいないけれど。
「桜、観に皆でいきましょうか、工藤ご夫妻にも声をおかけして。同窓生ってことで。ね、灰原さん?」
「ねぇ、円谷君、」愛が不意に立ち止まった。「それ、いい加減やめて」
「は?」
「名前」
「?」
「高校は小学校から一緒だった人達が結構いたから不自然じゃなかったけれど、これから…イチイチ説明していくの?」
「あ…ええと、じゃあ…」
「愛」
「…愛ちゃん…?」
「ちゃん付けする年じゃないでしょ、今更!」
愛は盛大に溜め息をつくと、すたすたと歩き始める。
「…!」
光彦は呼びかける言葉を失って、慌てて後を追った。
いくつか乞われてボタンをちぎってしまったので、制服がはためいて始末が悪いけれど。
愛は獣医になるつもりだ。
モルモットの気持ちがわかったから、と肩をすくめて、それを志望の理由のすべてにした。
志望学部を教えられたとき曖昧にされた意味が、ようやく嵌った。その感触が暖かなものを呼ぶ。
小熊に微笑みかけていた幼い少女の面影が今でも胸にある光彦は、夢を叶えた娘の姿を容易に思い描く事ができる。
その時、自分はどんな名前で愛のとなりにいるだろう。
まぁとりあえず…再度“同窓生”の肩書きを手に入れるところから始めようか。
|
fin
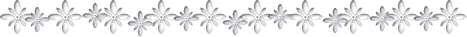
|